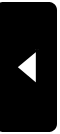2019年02月18日
「角打ち」=「かどうち」?「かくうち」?:校正者歴27年の男は漢字が得意か
少しずつ気温もあがってきたものの、
釣りビトにとっての極楽は、
まだもう少し先でしょうかね。
早く釣りの話題でブログ更新したいね。
「角打ち」、さあ、どう読むか。
ハイボールを口に運ぶ私に、その人(仮にH氏とする)は言った。
「角打ち、あれは『かくうち』じゃなく『かどうち』って読むんですよ」
私は「えっ……」と言葉に詰まった。
が、5秒の沈黙の後、告白した。
「かくうち、だと思ってました」
H氏は、「かどうち、なんですって」。
私は「そうだったのか……」としか答えられなかった。
(「かどうち」ね、「かどうち」。覚えたぜ)と
心の中で思いつつも実はまだ、
完全に信じきっているわけではないのが、
校正者という生き物の性(さが)だ。
しかしだ。
酒を酌み交わしているその場で、
すぐにスマホで調べるなんてのも野暮な話でしょ。
というわけで、その場では飲み続け、
あー、こりゃこりゃになった僕だ。
そもそも、なぜそんな話になったか。
お互いに釣りビトであり、出版関係であるH氏とは、
釣り関係の漢字の話になったのだ。
H氏が出席した釣り関係の場で、
ある人が、「わかんはさ」とか「わかんはね」と
「わかん」という言葉を大声で、
連呼していたのという。
H氏はこの人はなぜこんな場で「和姦」などという言葉を
大声で連呼するのだろう? と激しく疑問に感じたが、
そのうち「ああ、和竿(わざお)のことを言っているのか」と
気づいたのだという。
和(わ=音読み)+竿(さお=訓読み)を(重箱読み)せず、
音読み+音読みにしてしまったのだね。
知っている人だったが、今さらと思って
訂正はしなかったらしい。
というか、よほどの仲じゃないと、
そんなのを「おまえさん、間違っておるよ」などと
言えないよなあ。
……という話なんだが、その話を聞いた翌日、
「角打ち」を我が家の辞書で調べた。
我が家にある辞書は電子含め、以下の通り。
日本国語大辞典、大辞泉、新明解国語辞典、岩波国語辞典、広辞苑、明鏡国語辞典、小学館国語辞典
全部見たが、なんと、
「かどうち」と見出しがある辞書がない。
◆日本国語大辞典
かく‐うち 【角打】
解説・用例〔名〕
(1)、(2)略
(3)酒を升(ます)にはいったまま飲むこと。升飲み。
◆大辞泉
かく‐うち 【角打ち】
1 略
2 (四角い升の角に口を付けて飲むことから)酒屋の店頭で升酒を直接に飲むこと。転じて、店の一角を仕切って立ち飲み用にすること。また、そこで飲むこと。
3 略
◆日本方言大辞典
かくうち【角打】
(1) 升ますに入ったままの酒を飲むこと。
福岡県/ 熊本県下益城郡
(2) 酒屋で立ち飲みすること。
佐賀県/ 熊本県
《かくち》 熊本県玉名郡
《かくうちざけ【―酒】》 福岡市/ 佐賀県
(3)略
これは辞書じゃないが、
◆東洋文庫『江南春』青木正兒著
p104「酒の肴に塩」の中に、〈九州の田舎で往々「角(かく、とルビあり)打ち」という飲み方を見聞した。桝の角から冷酒を息をも吐かず飲みほすのである〉
なんだ。
「かくうち」でよかったのか。
自分の漢字に対する自信のなさで、
簡単に、ああ、そうだったのか、
「『かどうち』だったのか」と信じ込んでしまうのだ。
(完全に信じきっているわけではないのが、
校正者という生き物の性だ、とか言ってるくせに)
皆さん!
「角打ち」は「かくうち」ですよ!
このように、校正者は、あ、「校正者は」というと、
いろんな立派な校正者も含んでしまうので、
今ここにいる校正者歴27年の男は、
漢字が苦手である。
漢検2級に合格した後、1級の勉強を1週間やって
面倒くさくなってやめたが、
別に校正の仕事には何の支障もないので、
漢字に対する態度はまるで改まらず、
分からなかったらその場で(酒の場以外ね)辞書を引く。
それで四半世紀、飯を食ってきたのでいいのですね。
ちなみに現役校正者であるうちのカミさんに訊いてみると、
「え? 『かどうち』だと思ってけど、そう訊くってことは、『かくうち』?」、
ほおら、間違って覚えていた上に自信がない。
いい天気だな。
ゲラ読むのをやめて、
金魚釣りにでも行こうかな。
釣りビトにとっての極楽は、
まだもう少し先でしょうかね。
早く釣りの話題でブログ更新したいね。
「角打ち」、さあ、どう読むか。
ハイボールを口に運ぶ私に、その人(仮にH氏とする)は言った。
「角打ち、あれは『かくうち』じゃなく『かどうち』って読むんですよ」
私は「えっ……」と言葉に詰まった。
が、5秒の沈黙の後、告白した。
「かくうち、だと思ってました」
H氏は、「かどうち、なんですって」。
私は「そうだったのか……」としか答えられなかった。
(「かどうち」ね、「かどうち」。覚えたぜ)と
心の中で思いつつも実はまだ、
完全に信じきっているわけではないのが、
校正者という生き物の性(さが)だ。
しかしだ。
酒を酌み交わしているその場で、
すぐにスマホで調べるなんてのも野暮な話でしょ。
というわけで、その場では飲み続け、
あー、こりゃこりゃになった僕だ。
そもそも、なぜそんな話になったか。
お互いに釣りビトであり、出版関係であるH氏とは、
釣り関係の漢字の話になったのだ。
H氏が出席した釣り関係の場で、
ある人が、「わかんはさ」とか「わかんはね」と
「わかん」という言葉を大声で、
連呼していたのという。
H氏はこの人はなぜこんな場で「和姦」などという言葉を
大声で連呼するのだろう? と激しく疑問に感じたが、
そのうち「ああ、和竿(わざお)のことを言っているのか」と
気づいたのだという。
和(わ=音読み)+竿(さお=訓読み)を(重箱読み)せず、
音読み+音読みにしてしまったのだね。
知っている人だったが、今さらと思って
訂正はしなかったらしい。
というか、よほどの仲じゃないと、
そんなのを「おまえさん、間違っておるよ」などと
言えないよなあ。
……という話なんだが、その話を聞いた翌日、
「角打ち」を我が家の辞書で調べた。
我が家にある辞書は電子含め、以下の通り。
日本国語大辞典、大辞泉、新明解国語辞典、岩波国語辞典、広辞苑、明鏡国語辞典、小学館国語辞典
全部見たが、なんと、
「かどうち」と見出しがある辞書がない。
◆日本国語大辞典
かく‐うち 【角打】
解説・用例〔名〕
(1)、(2)略
(3)酒を升(ます)にはいったまま飲むこと。升飲み。
◆大辞泉
かく‐うち 【角打ち】
1 略
2 (四角い升の角に口を付けて飲むことから)酒屋の店頭で升酒を直接に飲むこと。転じて、店の一角を仕切って立ち飲み用にすること。また、そこで飲むこと。
3 略
◆日本方言大辞典
かくうち【角打】
(1) 升ますに入ったままの酒を飲むこと。
福岡県/ 熊本県下益城郡
(2) 酒屋で立ち飲みすること。
佐賀県/ 熊本県
《かくち》 熊本県玉名郡
《かくうちざけ【―酒】》 福岡市/ 佐賀県
(3)略
これは辞書じゃないが、
◆東洋文庫『江南春』青木正兒著
p104「酒の肴に塩」の中に、〈九州の田舎で往々「角(かく、とルビあり)打ち」という飲み方を見聞した。桝の角から冷酒を息をも吐かず飲みほすのである〉
なんだ。
「かくうち」でよかったのか。
自分の漢字に対する自信のなさで、
簡単に、ああ、そうだったのか、
「『かどうち』だったのか」と信じ込んでしまうのだ。
(完全に信じきっているわけではないのが、
校正者という生き物の性だ、とか言ってるくせに)
皆さん!
「角打ち」は「かくうち」ですよ!
このように、校正者は、あ、「校正者は」というと、
いろんな立派な校正者も含んでしまうので、
今ここにいる校正者歴27年の男は、
漢字が苦手である。
漢検2級に合格した後、1級の勉強を1週間やって
面倒くさくなってやめたが、
別に校正の仕事には何の支障もないので、
漢字に対する態度はまるで改まらず、
分からなかったらその場で(酒の場以外ね)辞書を引く。
それで四半世紀、飯を食ってきたのでいいのですね。
ちなみに現役校正者であるうちのカミさんに訊いてみると、
「え? 『かどうち』だと思ってけど、そう訊くってことは、『かくうち』?」、
ほおら、間違って覚えていた上に自信がない。
いい天気だな。
ゲラ読むのをやめて、
金魚釣りにでも行こうかな。
Posted by 亮太 at 14:15│Comments(0)
│近況